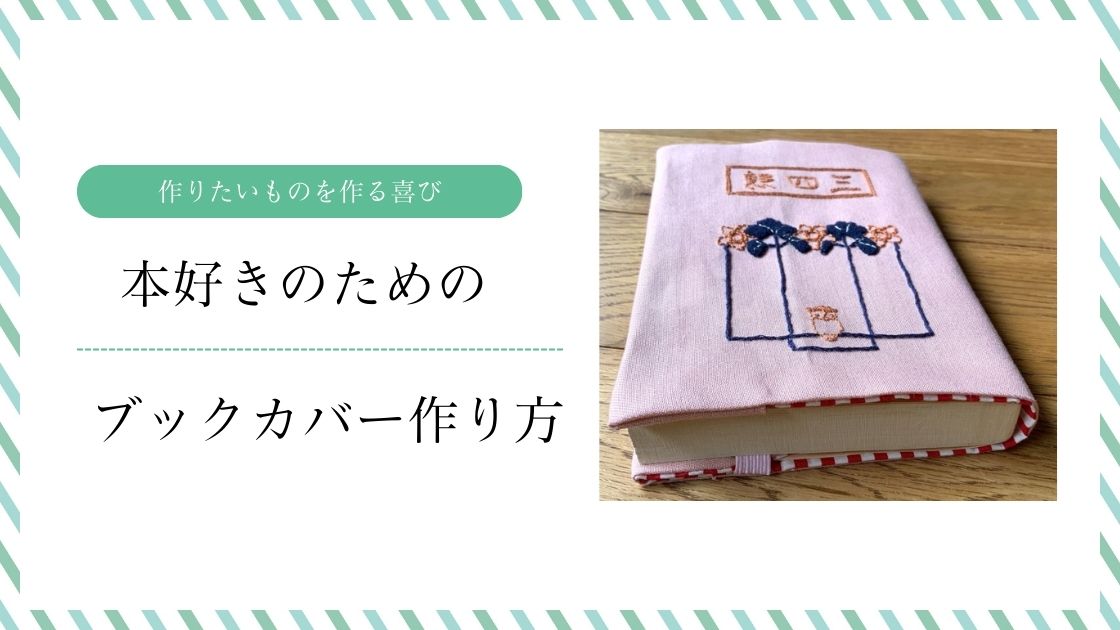先日、橋口五葉展に行って、作りたい!と思ったものがありました。
それが、布で作る文庫本のブックカバーです。
文庫本の場合は、書店で紙のカバーなどを自分でかけることもできますが、どうも味気ないし、バッグに入れていてもかわいくありません。
そこで、自分だけの文庫本のブックカバーを簡単にミシンで手づくりする方法を、お話しします。
目次
布製、文庫本のブックカバーの作り方・準備するもの
まず、準備するものです。
- ブックカバー用の布(表用と裏用)(サイズは後述)
- 1cm幅程度のゴムテープ:1cm幅程度のものを20cmぐらい
準備する布のサイズは、裏地を付けるか?どうか?で大きさが異なります。
裏地なしの方が、一枚の布で縫えるので、良さそうに思いますが、はぎれで作りたい場合には、長さが足りない場合があります。
それに、裏地があった方が、見た目的には綺麗なので、今回は、裏地付きにしています。
わかりやすいように、図を作りました。
※なお、今回、接着芯は使いません。
文庫本のブックカバー・布の裁ち方
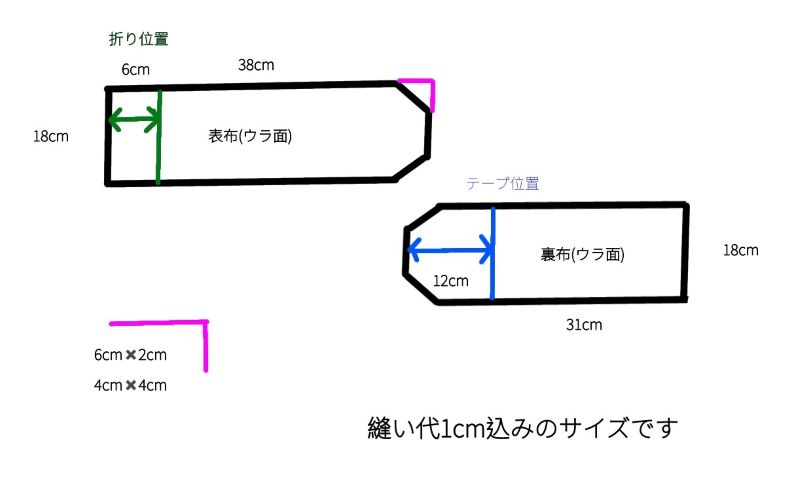
大きさは、
- 表布=横38cm×縦18cm
- 裏布=横31cm×縦18cm
が取れるサイズの布を用意します。
図のピンクの部分は、
- 横6cm×縦2cmか?
- 横4cm×縦4cmか?
どちらでもお好みのサイズで表布と裏布=4つの角をカットします。
さらに、
- 表布には、端から6cmの位置に印をつけ(折り位置)
- 裏布には、端から12cmの位置に印をつけます。(テープ位置)
文庫本のブックカバー・簡単な作り方
ブックカバーをミシンで縫う方法はいろいろですが、簡単などんでん返しで作ります。
作り方は、
- 斜めにカットしなかった方の端を縫う
- 表布と裏布を中表にして、間にテープをはさんで、周りを縫う
- ひっくり返して完成
たったこれだけです。
それぞれ、図解します。
斜めにカットしなかった方の端を縫う
布端の始末をします。
図をご覧ください。1cm手前に折って縫います。

表布と裏布を中表にして縫う
表布と裏布を中表にし、その間にテープをはさんで縫います。
- 布端の始末をした表布と裏布を図の向きに置きます
- 表布を折り位置で手前に折ります
- テープをテープ位置に置きます
- その上から、裏布を重ねます(斜めにカットした右側に合わせます→当然、左側は裏布が1cm短くなります)
- そのまま、赤い点線部分を縫い代1cmで縫います

ひっくり返して完成
左側(斜めにカットしていない方)は表布と裏布を合わせ縫いしていませんので、そこを返し口にして、ひっくり返します。
これで、出来上がり!です。
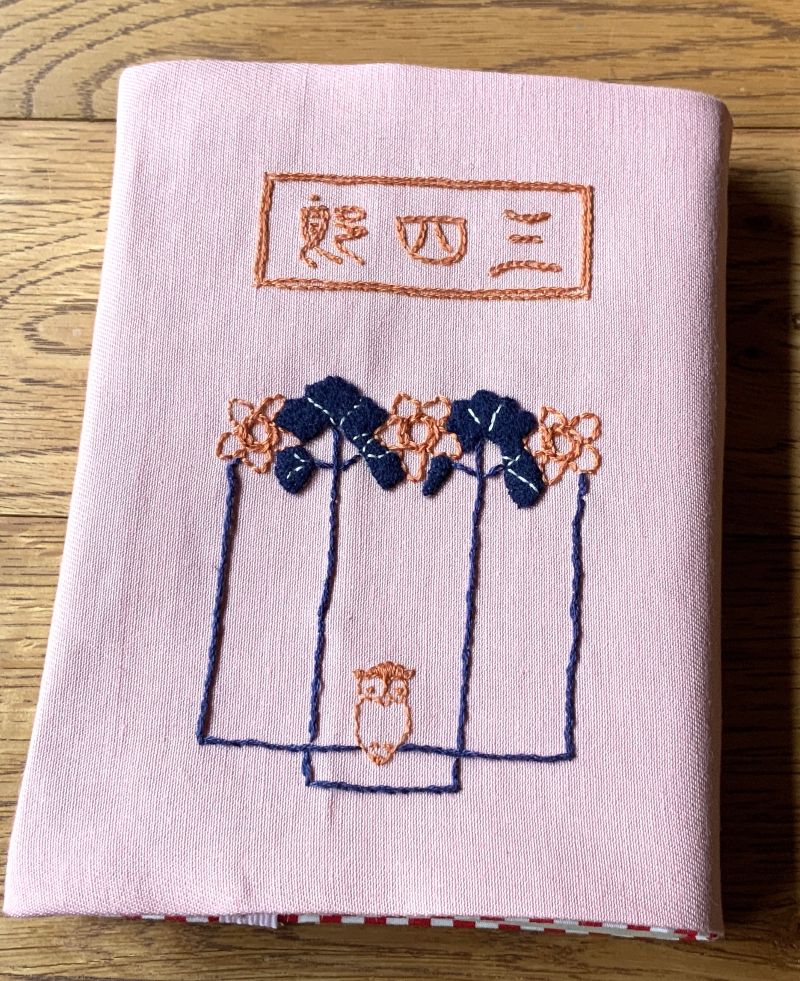
文庫本のブックカバー・その他の注意点について
文庫本のブックカバーの場合には、大きな布は必要なく、ハギレでも作れるのですが、布地は通常、布の縦を縦方向に置いて裁断しますよね?
そのため、ハギレによっては、大きさは十分だけれど、布の方向が違う!という場合もあるかと思います。
実は、私が選んだ「ハギレ」も、裏布はOKだったのですが、表布が⇔の方向でしか、サイズが取れませんでした。
そこで、試しに横向きで、裁断して作ってみたのですが、特に問題なく作れました。
ブックカバーは縫う部分も少なく、小物ですし、伸びまくる生地でなければ、大丈夫そうです。
また、ミシン糸の色は、表布に合った色を選べばOKです。
なぜなら、ミシン糸が見えるのは、表紙を差し込む部分だけだからです。(画像の矢印部分のみ)

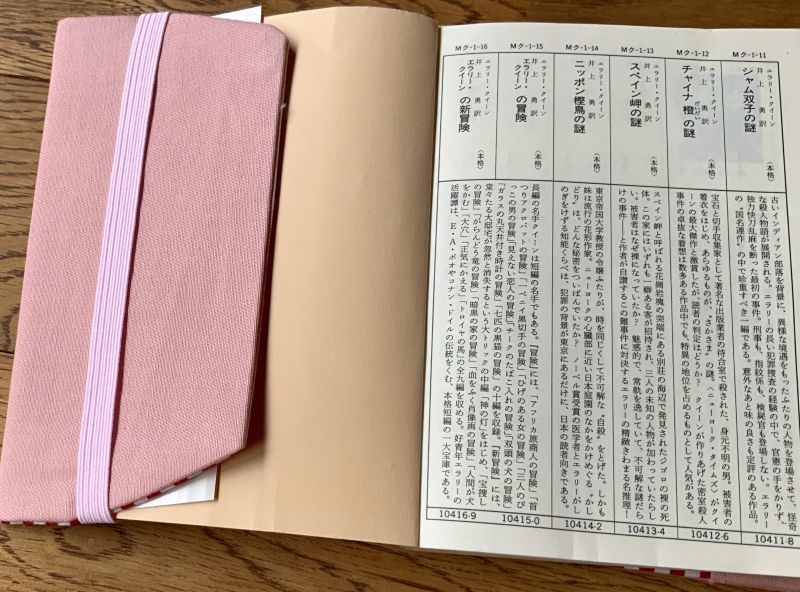
文庫本のブックカバーを布で簡単に手作りする方法のまとめ
文庫本のブックカバーを布で手作りする方法はいろいろ、ありますが、この方法が一番、簡単で、気楽に作れると思います。
また、サイズは、実際に作った時の感じから、私なりに調整しました。
ただ、私の場合、もともとは、橋口五葉がデザインした「夏目漱石の本の装丁」を見て、作りたい!と思ったわけですから、
ブックカバーを作る前に、まず!アップリケ刺しゅうをする!という工程がありました。
図案が細かいので、全部、刺しゅうの方がうまくいったかもしれませんが、アップリケ刺しゅうのプックリ感が好きなので、頑張りました。
当然のことながら、ブックカバー作成より、アップリケ刺しゅうの方に時間がかかったのですが、三四郎とみせかけて、実は中身はエラリークイーン(笑)と言うのも面白いな・・・と勝手に一人で満足しております。